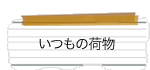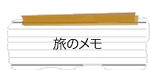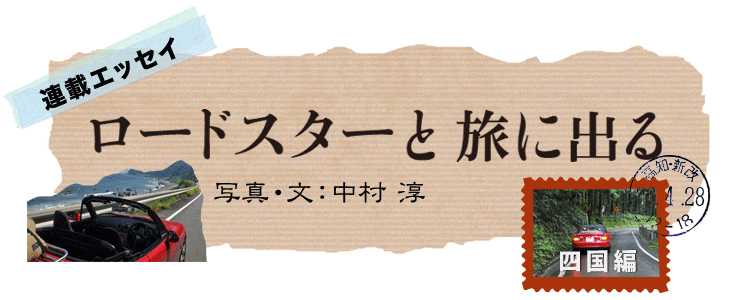
3.足摺岬はどこだ?
翌朝早くテントを這い出たが、もう彼のテントは跡形もなく消え失せていた。
朝食は珈琲だけにして私は出発することにした。
今日も申し分のない晴天で、相棒は一路南国土佐の高知市をめざす。
キャンプ場からちょっと下った先にある、第24札所「最御崎寺」の駐車場に相棒を停めて参道を登っていく。お寺を通りすぎて、その先の行き止まりが室戸岬灯台である。ゆるい登り坂を歩いていくと、暗くて狭い参道から眩しい海の風景へと劇的に変化した。
丸頭の灯台の向こうには、朝日にきらめく大海原がどこまでも広がっていた。静かだった。テレビモニターやスクリーンでは絶対に実感できない。ここに実際に来て、この天地に身を置かないといけない。何もない水平線が美しい。讃岐の空海がこの地で悟りを開いたと伝えられるが、室戸の海が彼の心を洗ったのかもしれない。自由律の俳人で有名な種田山頭火も遍路旅の途中に立ち寄り、室戸岬は真に大観であると、この景観に惚れ込んだ。病気、破産、離婚、流浪の人生最後に彼が選んだのは遍路旅だった。山頭火57歳の秋だった。翌年松山にて他界。
後から人が来る気配がしたので私はその場を立ち去った。私事ながら、そろそろ自分も山頭火の年齢になります。
スカイラインから室戸の漁港を見おろしながら、朝の空気の中を、相棒は一気にワインディングを駆け下りた。
ふたたび国道55号線を、高知めざしてハンドルをにぎる。
海岸沿いの道が続くが、コンクリートの堤防に遮られて海の展望は利きません。
やがて奈半利(なはり)の町へと走り込んだ。
ここにちょっと面白い庭があると聞いていたので、そこに立ち寄るつもりで交差点を右折する。古い家屋が続く道をすり抜け、川沿いの国道493号線を山に向かって遡っていく。道はとてもわかりやすく、めざす庭にはすぐに到着したものの開園は10時からで、まだ時間はたっぷりすぎるほどあった。
私はこういう場合、喫茶店で珈琲を飲みながら旅日誌をつけるのが常なのだが、あいにく適当な店が見あたらない。そこで奈半利川沿いをさらに山奥へと遡り、北川村温泉に浸かってから戻ってきた。オープンを待って入浴したので客は地元のお爺さんと二人きりだった。湯があふれるさらさらという響きしかしない。山間の静かな朝。泉質は透明でやわらかな湯で、昨夜はキャンプ場のコインシャワーでささっと汗を流すだけで済ませたため、朝一番の温泉は極楽だった。今頃オフィスであくせく働いているであろう同僚たちのことを想うと、ちょっと申し訳ない気がしたが、日頃からご無理ごもっともで頭を下げているサラリーマンにとって、有給休暇こそが唯一の特権なのだから大きな顔をしていればいいと思い直した。
この北川村は柚子の産地で知られ、毎年11月の収穫時期には村中が柚子の香りに満たされるそうな。
さて私は北川村温泉をあとにして、モネの庭マルモッタンに乗りつけた。
100台は入るであろう広い駐車場には、ほんの数台が肩を寄せ合うようにして停まっているだけだった。
印象派の巨匠クロード・モネの名は、絵画に興味がない人でも、一度や二度は耳にしたことがあるかもしれない。晩年彼が自分の庭に作った睡蓮池から、いくつもの名作が世に送り出されたのは、多くの絵画好きが知るところでであるが、そのフランスにある庭を、ここ日本に再現したのがこの庭で、フランスにあるモネの庭の管理者が監修にあたったと言われている。
入園料を払い、目指す池を捜しながら散策路をあがっていく。
しばらく登っていくと、印象派のモネの絵画に出てくるような橋やアーチがあり、緑にかこまれた池のあちこちには、鮮やかな赤や黄の睡蓮が花をつけていた。他ではあまり見ない青い睡蓮も咲いていた。
私はアーチの傍に大輪の花を見つけてカメラで接写した。
撮り終えて振り返ると、30歳と思しいひとりの女性が立っていた。その手には本格的な一眼レフのカメラが握られている。私は軽く会釈をして場所を譲った。最近は女性でも本格的なカメラを持って旅をしている姿をよく見かけるようになった。技術革新で軽量になったうえに、コンピューターのおかげで露出計を気にすることもなく撮影できるせいかもしれない。でも男の私はちょっと寂しい気もしてしまう。なぜならまるで家電製品のような便利さのせいで、精密機械を使いこなす楽しみがなくなったからである。世の中が便利になればなるほど、男の夢が萎んでいく気がしてやはりちょっと寂しい。カメラに限らず、男が夢を見る余地を残しておいてもらいたいものです。
私は散策を続けた。
夏は緑が勝って花が少々寂しい。
次回来るときはバラの季節しようと思いながら歩いていると、私のすぐ先をさっきの女性が歩いているのに気がついた。ひとり旅のようだった。私は道の向こうに黄色い花を見つけ、それを撮ろうと思った。すると彼女が足を止めて先にレンズを向けた。今度は私が順番を待つ。そんなことが数回くり返され、お互い笑顔で会釈を返した。
私はレストランで朝食を兼ねたランチを済ませると、ゆったりとした気分でコクピットに身を沈め、マルモッタンの丘から走り出た。
真夏の太陽に干された丘を降りていきながら、空が広いこの道を、花の季節の風に吹かれながらオープンで走ろうと想った。どんなにか気持ちが良いことだろう。
さっき走ってきた国道493号を、今度は海に向かって戻って行き、ふたたび海沿いの国道55号を高知に向けてアクセルを踏んだ。
今日のもうひとつの楽しみは四国自動車博物館で、
4輪2輪の旧車名車が多数動態保存されているはずである。私はトヨタ2000GTとアルファ・ジュリエッタスパイダーの造形に興味があったので、実物を拝めるのをとても楽しみにしていた。ナビもなく不案内なのだが、香南市にある龍馬歴史館のすぐ傍のようだった。
いざ香南市めざしてアクセルを踏み込んだ。
その時、ふといやな予感に囚われた。
昨日は日曜日だったので、言うまでもなく今日は月曜日のはず。
ひょっとして月曜は休館だったか?
私の旅は、とても用意周到と呼べるような代物ではなくて、旅に出てしまえばあとは何とかなると思っている方です。
うーん次回四国に来るときは、絶対にバラの季節に来て、そして絶対に自動車博物館まで足をのばそう。
結局、香南市のずっと手前、道の駅「やす」に相棒を停めて、2階の喫茶室から広い砂浜とビーチバレーの練習を眺めながら旅日誌を書いた。思いのほか美味いアイス珈琲に行き当たったのが収穫といえば収穫だった。
国道55号は高知市で32号と名前が変わり、私と相棒は夕方の渋滞の列にならびながら、はりまや橋の交差点を過ぎ、めざすユースホステルに投宿したのでした。
翌朝は県道34号線を南下して海岸沿いの県道14号線へと走り込んだ。
桂浜は昨今のドラマブームで混雑が予想されたのでパスすることにし、
今日はいよいよ二つ目の岬である足摺岬をめざす。
須崎市で横浪黒潮ラインを選び、複雑に入り組んだ海岸線を見おろしながらのドライブを楽しんだ。小さなオープンカーの開放的な悦楽を味わう。
道の駅「かわうその郷すさき」にて土佐名物一本釣りの鰹のたたきを買い、クール宅急便で家族に送る。いくぶん値が張ったが、留守番役の家族へのケアは大切です。ここでは鰹のたたきの藁焼き実演が見られる。何か他に面白そうなものはないかと物色していると、一本釣り鰹カレーなるレトルト商品を見つけた。発売したばかりだという。さっそく購入。これは今夜のキャンプ用。
須崎市からは国道56号線を軽快に走り続け、中村の街で四万十川を渡った。
ここで思わぬルートミス。
四万十川を渡ってすぐを左折して国道321号線を南下するのが足摺岬への道だった。私はうっかり忘れてしまい、ひたすら56号線を走り続けた。
行けども行けども足摺岬はなかった。
やっと海が見えたと思ったら、そこは宿毛の街だった。そこからさらに北上を続ければ宇和島に向かう。反対に海岸線を南下すれば大月を経て足摺まで戻ることができる、と地図に描かれてあった。
私はハンドルを左に切り、国道321号線(通称サニー道路)を南下した。足摺岬まではかなりあったので、今日は無理をせずに明日に立ち寄ることにした。時間が出来たので海水浴で人気の柏島まで行ってみた。海はきれいだが人が多すぎて雑雑として落ち着かない。私は少し戻ってエコロジーキャンプ場に相棒を入れた。
ここのオートキャンプ場にはスノーケリングセンターがある。それは初心者でもスノーケリングが手軽に楽しめる施設で、すぐ目の前の広い浜から海に入って磯まで泳いでいくので、子供でも安全にエントリーができる。
係の男性は人懐っこく、話が弾んだ。
南風で濁りがやや入っているが、沖へ出れば濁りはマシだという。ポイントを教えてもらって、私は自分の素潜り3点セットでさっそく潜ってみた。たしかに海岸寄りは濁り気味だったが、沖に出ると透明な海が待っていた。南の海らしく珊瑚の上をチョウチョウウオが舞う。大きな錦色のブダイが悠々と目前を泳ぎ、カマスの美しい群れに遭遇した。南伊豆の中木でシュノーケリングを楽しむのが私のいつもの夏なのだが、今シーズンはまだ訪れていなかったので、ほぼ1年ぶりのスノーケリングになった。久しぶりで大いに楽しんだが、ただ珊瑚に元気がないのが気がかりだった。
「台風で崖が崩れて大量の土砂が海に流れ込んだのです」
センターの男性が指さす先には、海岸に沿って修復されたばかりの痛々しい崖が見えた。その土砂に覆われて珊瑚が大きなダメージを受けたという。珊瑚を食い荒らす貝も大量発生したらしい。幾つかの要因が重なって、今、珊瑚は力をなくしている。
「以前は、潜れば足の踏み場もないほどにテーブル珊瑚がいっぱいありました」
そして珊瑚の移植が始まり、徐々に成果が出つつあるという。
明日こそ足摺岬をめざします。
天気予報では、明日はあいにくの天候になりそうだった。