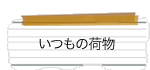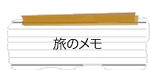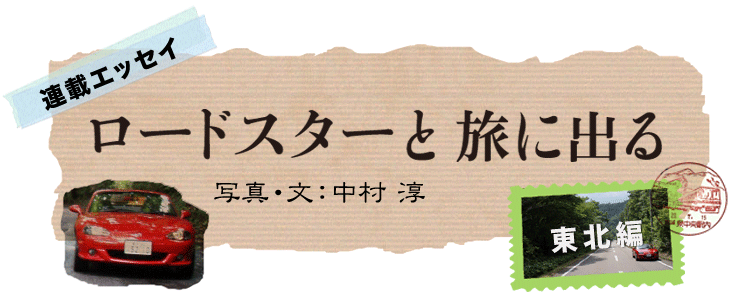
3.弘前から白神山地越え
私は103号線を走って濃霧の八甲田山から青森市内まで下りてきた。版画家の棟方志功記念館、縄文遺跡の三内丸山の発掘現場、県立美術館で特別展「太宰治と美術」を見てまわり、国道7号線を弘前まで南下してルートインに投宿。コインランドリーとベッドにありつくことができた。
明けて、今日は三つ目の山塊である白神山地を走る。
13万ヘクタールもの広大な山地の北端を横断する林道が白神ラインである。その中心部の1万7千ヘクタールが、1993年12月に日本初の世界遺産としてユネスコに登録されたことは有名です。
今日も天候が気がかりだった。山深く走り込むのがためらわれるほどの厚い雲である。街で給油をすまし、県道28号線を岩木川に沿って山懐に分け入っていく。快適なカントリーロードを楽しむ。途中ビジターセンターにて白神山地ガイドマップを調達した。多目的ダムの美山湖を通り過ぎたあたりから急に山が深くなった。きついブラインドカーブが連続し、車両感覚の正確さが試されるようだ。美山湖のバックウォーターにアクアグリーンビレッジという観光施設がある。ここに停めて暗門の滝まで散策の予定だったが、増水で遊歩道は閉鎖されていた。私はビレッジのセンターハウスにある受付に出向いた。ここにテントを張ってベース基地にして荷物をすべて降ろし、身軽になった愛車を駆って白神ラインのドライブを楽しんで途中で引き返してくるつもりだった。しかし一部工事中だったラインも全線通行可能とのことなので、一気に白神山地越えをして、日本海側まで出ることにした。
相棒のコクピットに身を沈め、キーをひねる。
ビレッジを走り出て県道に別れを告げると、いよいよ白神ラインである。走りやすいフラットダートだ。コーナーの手前でアクセルをゆるめて軽くフェイントをかけ、ハンドルを切り込むと同時にアクセルをじわりと入れると、後輪からザーという音が響いてロードスターはリヤをスライドさせ、面白いようにノーズをインに向けていく。インに向いた時点で少しハンドルをもどし、そのままハーフスロットルを維持していると、軽いドリフト感を味わいながら不安なくコーナーから立ち上がっていく。
さり気ない最小限のドリフト量でクリアしていくのが良いと私は思います。
これぞ人馬一体なり!
もう面白くて無我夢中になって走っていると、対向車がいきなり現れて肝を冷やした。ABSが作動して何とか停止できた。向こうも相当に飛ばしていた様子でかろうじて停止した。お互い軽く手で挨拶を交わして発進させた。横浜ナンバーのインプレッサだった。それからは多少慎重になったものの、また知らずペースが上がっていく。とにかく楽しい。我ながら子供みたいだと思う。これもロードスターの悦楽。
あっという間に津軽峠まで来ていた。
全体50キロのうち10キロほど走った勘定である。広くはないが整備された駐車場があって、バスから数人のハイカーが降りて散策路へと歩いていく。ブナの巨木「マザーツリー」を見に行くのだ。登山バスはここで折り返してビレッジまでもどるようだった。私は気分が乗っていたので、アクセルを踏み込んで通過した。
いよいよ山深く走り込んでいく。
路面の状態は激変した。いきなり狭くなり、路面は荒れ放題。スピードをうんと落とさざるを得なくなった。これが白神ラインの本当の姿だと気づかされた。さっきまでの快適なフラットダートは、バス路線のためにメンテされてあったのだ。ロードスターにはちょっと酷な山越えになりそうだったが、私は敢行することにした。
狭いカーブの応酬が始まった。
さっきまでの比ではない。路面の荒れはどんどんひどくなる一方で、こぶし大の石が地面からぼこぼこと頭を出している。浮き石も多くて、右に左に巧みに避けながらスピードを維持していく。ギャップを斜めによこぎる。ハンドル操作がやたら忙しくなった。ある意味人馬一体だったが、時々失敗してがつんと乗り上げたり、石を前輪で弾いて車のヘソのあたりでカーンとかキーンとか金属製の澄んだ音が響き渡った。速度は20キロ以下。それ以上は無理な相談である。車体全体がバイブレーターになったみたいだった。全身の凝りがほぐれるなどと強がりを言っている場合ではなくなった。ハンドルを持つ手がしびれてきて休憩が必要だった。標高が上がってくると、ところどころ路肩が広くとられて展望所になっていた。そこで車から降りて保護区が広がる南方を見やると、ブナの原生林が幾重もの山ひだになって見わたせた。
静かである。ブナの巨木が多いせいか山全体がもこもこした感じで、山肌は平坦ではなく力を感じさせる。
一息ついてまたアクセルを踏む。
山深いといってもブナの森は明るくて、さわやかな緑のトンネルがどこまでも続いている。これぞオープンカーのだいご味などと悦に入っていたら、ほらいきなりの雨です。ばらばらとブナの葉を叩いて、みるみる山全体が驟雨につつまれていった。スピードが上がらないので雨滴がコクピットに降り込んでくる。新鮮な山の緑は雨さえ心地よく、しばらくは火照った肌に冷たい感触を楽しんでいたが、そうはいっても、やはり路肩に寄せて幌を閉じた。しかしオープンで走る心地よさに、雨が降ったり止んだりするなか、そのつど幌を開け閉めし続けたのだった。
さらに道幅は狭くなり、樹木も鬱蒼としてきた。
左側が谷になっている。路肩にはガードレールも何もない。密集した樹木に遮られてよくは見えないが崖のようである。対向車が来たらちょっとやっかいだなと身がまえながら走っていると、道幅の右半分ほどが工事用の仕切で通れなくなっていた。落石か崖崩れの後片づけだろうか、いずれにせよ今日は作業はしていなかった。私は左の谷側ぎりぎりに寄せて2速に落とした。路肩に二人の作業員がならんで立っている。私はさらにスピードを落として彼等の前を通過した。
その時、私は奇妙な物を見た。
それは二人の作業員の足下の地面だった。路肩にロウソクが二本灯されていたのだ。二人に護られているようにも見えた。周囲が暗いので、その灯火は私の目にくっきりと焼きついた。
やっと峠を越えて、林道は下り勾配になった。
向こうからマイクロバスがゆっくりゆっくりと上がってくるのが見えて、私は展望所に愛車を入れてやり過ごすことにした。バスには半分ほどの乗客しかいなかった。窓の外に向けられた目はどれも虚ろで暗くしずんでいた。路線バスでもなければ観光バスでもなかった。翌日、白神岳の山頂にて、すべての理由があきらかにされたのでした。
ようやっと十二湖まで降りてきた。ここまで来れば日本海は目と鼻の先。
アスファルトには雨の痕跡さえ見いだせない。アクセルを思いっきり踏み込めば舗装道路のありがたさが身にしみた。十二湖ビジターセンターに入れて人心地つく。こぢんまりとした誰もいない展示室を見てまわると、自分の靴音だけがやけに響きわたる。ややあって、入口の方で華やいだ声がした。その声が飛んできて背中にぶつかった。
「すみません。すっごく大きなお魚がいるって聞いてきたんですけど……」
顔を上げると、街から観光に来たらしい女子大生ふうがふたり立っていた。あらためて私は展示室を見まわしてみたが、それらしい写真も標本も見あたらなかった。むろん水槽もない。渓流に棲むのはヤマメかイワナで、大きくなってもせいぜい30センチくらいだ。私は釣りをやるので判るが、若い子だからきっと誰かにからかわれたのかもしれない。
「こんなところに大きな魚はいないと思いますよ」
残念そうにしている彼女たちをそのまま残して、私は表に出た。泥だらけの相棒が一台ぽつりと停まっている。早く洗車してやりたいものである。撒水栓のひとつもないかと思いつつ建物の裏手にまわってみると大きな池があった。そこに生け簀が作られてあって魚がいたのだ。それも"すっごく大きなお魚"が。70センチはあろうかと思われる黒い丸太のような魚が群れていた。こんなところでイトウが養殖されているとは夢思わなかった。北海道の釧路湿原に生息する幻の魚として有名である。
「おーい、こっちこっち」
表に出てきた彼女たちに声をかけた。二人はイトウを見るなり目をまん丸にして
「わ、すごい」
と発したきりでじっと見入っている。街でよく見かける若い子達の大袈裟すぎるリアクションはない。こういう自然で素直な女性の反応に私はめっぽう弱い。好感を抱きつつも、ふたたび車上の人となったのでした。
私は十二湖周辺を走りまわってから、キャンプ場をめざした。
道路の端を彼女たちが歩いているのが目に入ってきた。駅まで歩くようだった。ここからだと30分は優にかかるだろう。送って行ってあげようと思った。小柄な人たちだから何とか乗れる? 縦に重ねる? 横に押し込む?
先日、十和田湖畔で会った男の笑い声を思いだしていた。
私はリフレッシュ村にテントを張り、北欧風ログケビンのサウナで気持ちのいい汗を流した。白神山地の美しい水と、盛岡で買ったばかりの香ばしい珈琲豆。その美味い珈琲をゆったりと楽しんでいるところに、さっきからポツポツ落ち始めていたのが、いよいよ本降りになった。本当に容赦がない。その夜はまた大雨に見舞われ、風が一晩中吹き荒れたのだった。
白神ラインは、
その1.困難な旅を愛馬とともに乗り切った一体感が欲しい人。
その2.白神山地の深さを肌で感じたい人。
その3.車高を下げていない人。
以上、この三つを満たさない人にはお勧めではありません。津軽峠で引き返しましょう、老婆心ながら……。